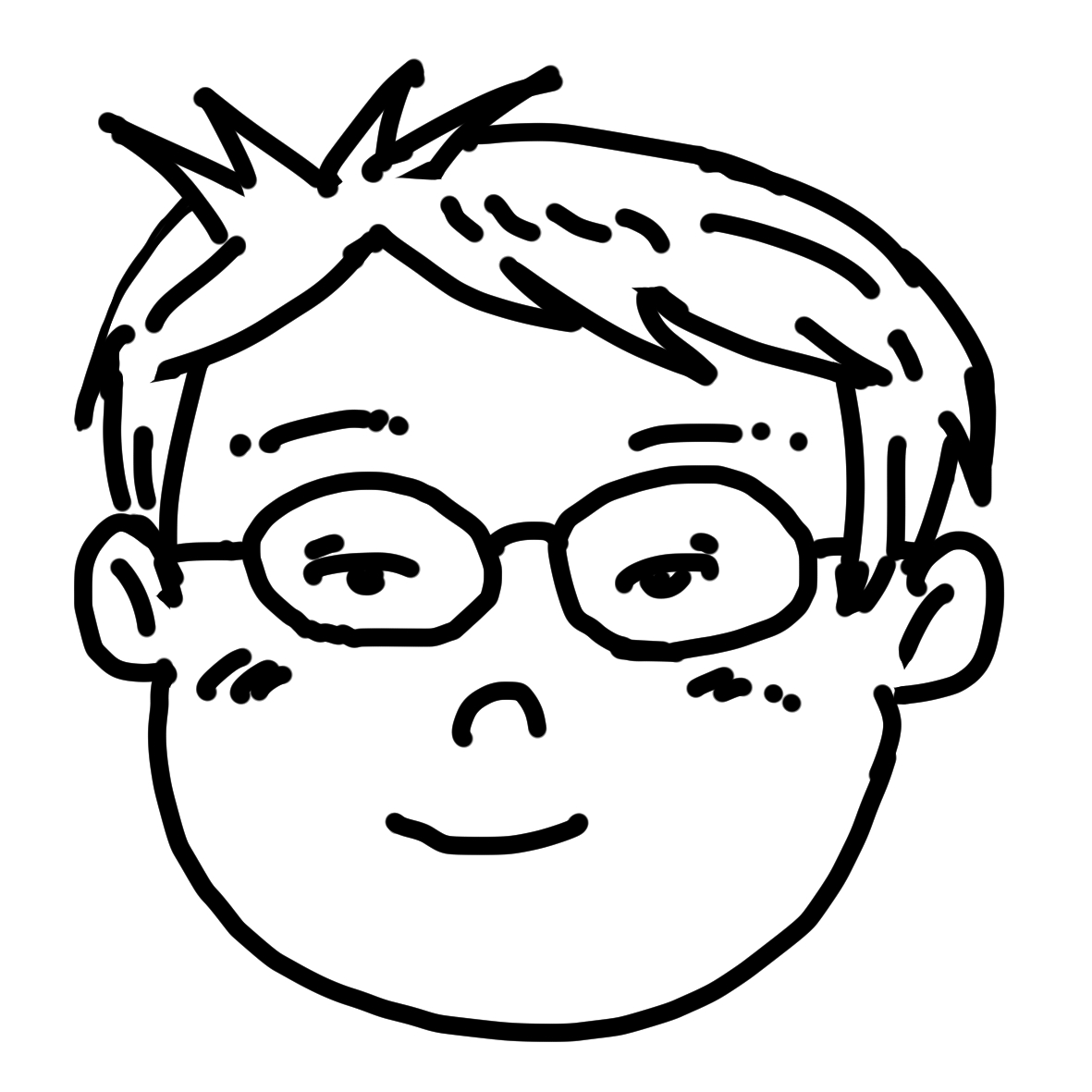守貞漫稿「灰買いなどの行商」(一番左側が灰買い)
江戸時代は、各家庭に竈(かまど)があり、そこで煮炊きをしていました。そして、その燃料は、木材や藁(わら)でした。江戸や京都、大坂は巨大都市でしたので、それらを燃やした結果として大量の灰が出ます。各家庭にとっては、種火を残すなどのために多少の灰は必要でしたが、大量に出る灰の殆どは不要の長物でした。現在の私たちの感覚からすると、灰は使い道の無い単なるゴミの山ですね。しかし、実は様々な活用方法があり、宝の山だったのです。江戸時代、この宝の山である灰に目をつけ、町中から灰を集めて回る「灰買い(はいがい)」と呼ばれる人たちがいました。

「新板かつて道具尽」右下が江戸時代の竈(かまど)
¶ 不思議な性質を持つ灰
木や藁を燃やして出来た灰は、様々な不思議な性質を持っていることを昔の人々は知っていました。今考えると、灰はアルカリ性ですので、色々と納得できますが、昔の人は経験則から学んでいたのです。関西では、藍染めの時に繊維を脱色させたり、濁り酒を澄ませたりと活用されていました。また、江戸近辺では、田畑の土壌改善に利用されていました。今日は、江戸時代の人々がどのように単なる燃えカスの灰を使ったかを解説していきます。
¶ 藍染に使われた灰

名所江戸百景「神田紺屋町」(染物の町)
藍染は、普通の草木染と染め方が全く異なります。発酵という微生物の働きにより染めていく技法です。この藍染の際のポイントとなるのが、灰汁です。灰汁とは、木灰を水に浸して作った上澄液の事です。灰汁を使った藍染め液は、単なる藍染め液と比較すると、そのアルカリ性が上手く作用して鮮やかな藍の色が出ます。
藍染自体は、飛鳥時代からありましたが、江戸時代になると庶民の間で流行し、爆発的に広がっていきました。従って、灰の需要も爆発的に増え、非常に価値の高いものになり、豪商が産まれていったのです。
¶ 京都の灰屋 紹由と紹益

井原西鶴「好色一代男」(吉野太夫)
江戸初期の京都で、灰屋紹由(はいや しょうゆう、じょうゆうとも)という商人がいました。元々は、藍染め屋だったのですが、その材料に使う灰を商売にして、巨万の富を築き、豪商になったのです。
紹由は、連歌や書、茶の湯などの風流の道を好み、風流三昧の生活を送ったといわれています。あの古田織部(戦国武将で、千の利休の弟子。「へうげもの」という漫画の主人公でしたね。)とも親交があったほどでした。ところが、紹由には跡継ぎがいませんでした。そこで、養子を迎えます。それが、紹益(しょうえき)ですが、紹由の期待と反し、商売には全く目もくれません。紹由以上にひたすら風雅と遊びの道を歩みます。和歌は烏丸光広から、俳諧は松永貞徳から、茶の湯は千道安から、書は本阿弥光悦からといった具合に一流の人物から学んだり、島原の遊郭に通ったりと、豪遊を繰り返しておりました。その暮らしぶりは、井原西鶴の浮世草子「好色一代男」の世之介モデルになったほどでした。
この紹益、灰にまつわる凄まじい話が残されています。それは、御推尾天皇の弟と争い見受けした遊女の吉野太夫にまつわる話です。父紹由の反対を押し切り、やっとのことで吉野太夫を妻として迎えることができますが、僅か10年ほどで吉野太夫は亡くなってしまいます。落胆した紹益は、その遺灰を毎日少しずつ酒に入れて、吉野太夫を偲びながら飲み干したという話です。よほど愛が深かったのでしょうが、灰屋とはいえ、凄い話ですね。
¶ 酒の加工に使われた灰

日本山海名産図会「伊丹酒造」米洗いの図
やはり、江戸時代の初め頃の話です。伊丹に鴻池新六がやっている酒造がありました。その頃の日本酒は、現在のような澄んだ清酒ではなく、濁り酒でした。
ある日、使用人がお金を使い込んでいることを、主人の新六は気付きます。新六は怒って蔵からその使用人を追い出します。ところが、あろうことがその使用人、腹いせとして、仕込み中に酒に灰を投げ入れて逃げてしまいます。頭を抱えた新六ですが、翌朝もう一度、酒樽を覗くと、不思議なことに澄んだ酒が出来ています。恐る恐る飲んでみると、さらに不思議なことに酸味が抑えられた芳香な香りと味のお酒に変わっていました。
こうした偶然も手伝い、灰の効用を発見した新六は、その後、研究を重ね、美味しい透明なお酒を世に出し、豪商に成長したとのことです。これが、かの鴻池財閥の始まりとされています。
今では、酢酸を抑えるために灰を使うことは殆どないのでしょうが、現在のような美味しい日本酒が飲めるのも元を辿れば灰とお行儀の悪い使用人のお蔭だったとは、驚きですね。
¶ 土壌改善に使われた灰
江戸では、周りの土壌が、関東ローム層と呼ばれた火山灰が降り積もって出来た酸性のもので、作物を育てるには非常に不適なものでした。従って、灰で土壌を中和させるのに使っていたのですね。江戸は百万都市でしたので、大量の食料が必要です。それを支えた近郊の農業、そしてその生産性を高めるために使用された灰は、非常に貴重な資源だったわけです。
¶ 江戸の灰買いとは?
 このような理由で、江戸時代の江戸の町には、残った灰を買い取る業者が活躍していました。灰買い(はいがい)と呼ばれていました。「へっつぅーいなおし、へっつぅーいなおし。灰はたまってございませんか、灰屋でござい~」などと、声を出しながら、長屋を廻っていました。結構、大変な仕事だったようで、いつも髪の毛は灰だらけで、若いのか年寄りなのかわからない有り様だったとのことです。
このような理由で、江戸時代の江戸の町には、残った灰を買い取る業者が活躍していました。灰買い(はいがい)と呼ばれていました。「へっつぅーいなおし、へっつぅーいなおし。灰はたまってございませんか、灰屋でござい~」などと、声を出しながら、長屋を廻っていました。結構、大変な仕事だったようで、いつも髪の毛は灰だらけで、若いのか年寄りなのかわからない有り様だったとのことです。
各家庭では、かまどに残った灰を箱に入れて貯めておきます。また、湯屋(今の銭湯)や大店(おおだな)などの大量に灰が出るところは、灰小屋に灰を貯めておきます。灰買いは、定期的にこれらを廻って灰を買い取っていました。集められた灰は、江戸の場合は主に肥料として売買されました。特に川越では定期的に灰市(はいいち)が立ち、その周辺には灰問屋もあったとのことです。
¶ 洗濯にも使われていた?
灰の利用方法としておまけにもう一つだけ紹介しておきます。左側にある浮世絵を見てください。浮世絵師の鈴木春信の「持統天皇洗濯物干」(東京国立博物館所蔵 )です。よく見る洗濯をしている女性の横に底に近い部分に栓のついた樽がおいてあります。この樽は何なのでしょう。
実は江戸時代の嫁入り道具に一つで、竈の灰と水を混ぜ、灰汁を作り、溜めておくものでした。何に使っていたかというと、なんと洗濯の時の石鹸代わりでした。タライにこの灰汁を入れて、もみ洗いしていたのです。

鈴木春信「持統天皇洗濯物干」(拡大部分図)
¶ 循環型社会、江戸から現在へ
意識していた訳ではないでしょうが、江戸という時代は、最後の最後まで絞り尽くすように資源を使っていたのですね。燃えかすの灰さえも循環され、肥料として使われ、今度は食料として人々の口へと渡っていました。それは、今で言う「エコ」という言葉を使うのが恥ずかしくなるほど徹底しており、循環型社会の一つの完成形だったと言えます。一方、現在の私たちの社会はどうでしょうか?次から次へと家電や電子機器が使われ、再利用されることなく、廃棄されたり、死蔵されたりしています。2000年頃から、都市の金山と言われた携帯、そして現在のスマホも、家庭に眠ったままになっていることが非常に多いことでしょう。でもそろそろ、新しいムーブメントが始まる気配がします。何周も時代は巡って、また江戸時代のような循環型社会が、もうすぐそこまで来ているのかも知れません。
特集「江戸のリサイクル」
第1回:江戸のリサイクル1…こんな昔に再生紙
第2回:江戸のリサイクル2…灰買いとは
第3回:江戸のリサイクル3…ゴミの行方
第4回:江戸のリサイクル4…江戸の町は化学工場
第5回:江戸のリサイクル5…修理屋
第6回:江戸のリサイクル6(最終回)…回収業者