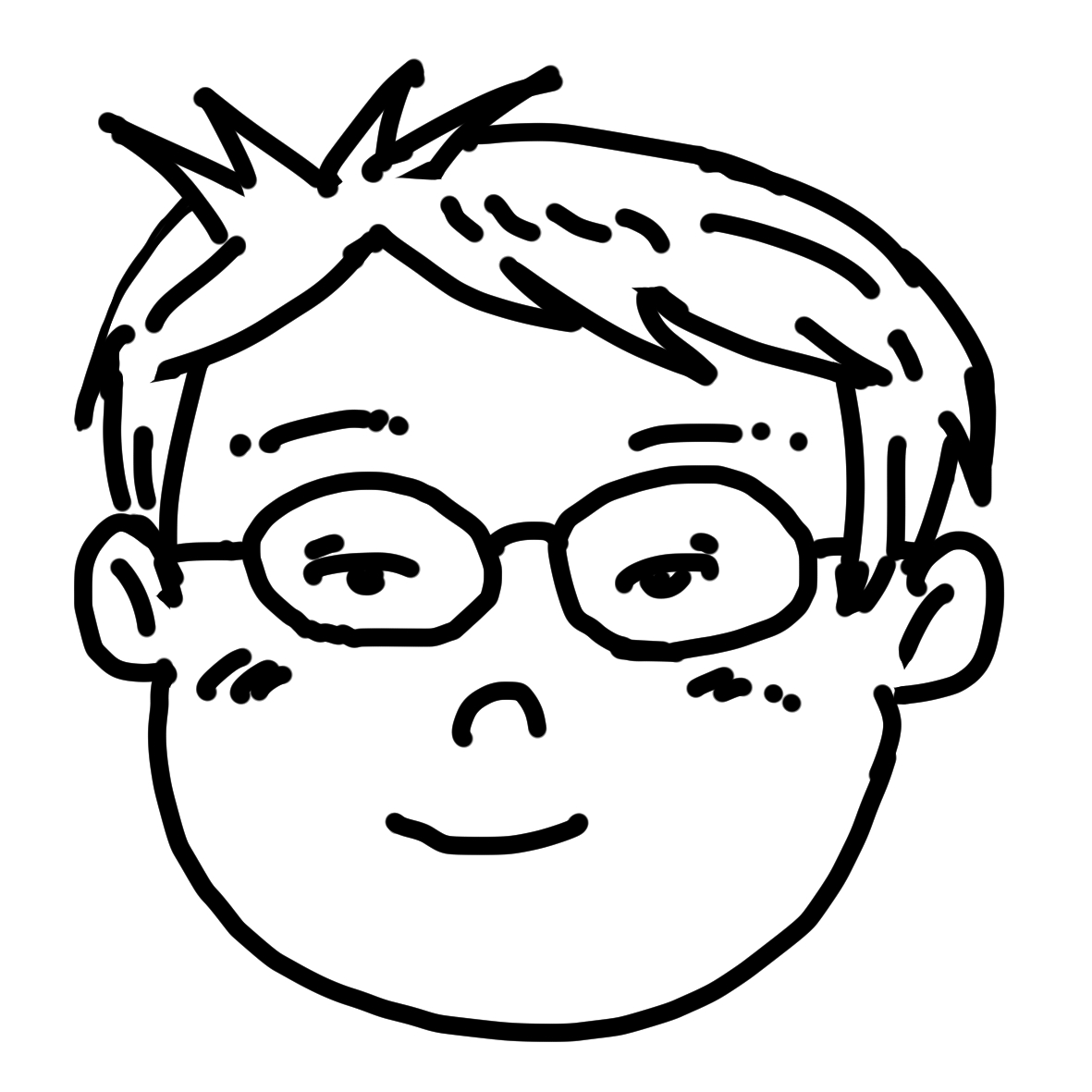今回は、人工衛星も飛行機もなかった時代に、驚異的な精度の日本地図を製作した伊能忠敬(いのう ただたか)の物語です。紀元前7世紀頃、小アジアの西部(現トルコ共和国西部) にマグネシアという町がありました。 そこでは磁性を帯びた不思議な石が産出され、 人々はその石のことを「マグネシアの石」と呼んでいました。 その後、2000年近くを経て、このマグネシアの石で作られた杖先羅針(つえさきらしん)という方位磁石を使い日本中を測定してまわる者が現れます。それが伊能忠敬でした。
¶ 推歩先生

佐原(現在の千葉県佐原市)の酒造家の伊能忠敬は、酒造の他にも、運送、金融、米相場などの多角経営で大成功を収めていました。ところが、49歳の時、突然隠居し、家督を息子に譲ります。そして、寛政7年(1795年)50歳の時、忠敬は江戸に出てきて、当時、新暦編纂のため、大阪より江戸へ出てきたばかりの高名な暦学者、高橋至時(たかはし よしとき)に師事します。暦学とは今でいう天文学のことです。この時、なぜ、暦学だったかは不明ですが、当時の理系好きは、数学、暦学と修めていくのが通常だったからのようです。ただ、不思議なのは、一介の商人が幕府の暦局の暦学者に弟子入りしている事です。普通では、考えられません。もしかしたら、豪商だった伊能忠敬は、観測器具などの援助を条件に弟子入りが出来たのかもしれません。そんなうがった見方はともかくとして、弟子となった忠敬は、至時の予想に反し(20近くも年上かつ大金持ちの忠敬のことを当初は年寄りの道楽くらいに考えていたと思います。)、メキメキとレベルを上げていきます。寝る間も惜しんで勉強する忠敬は、至時から「推歩先生(すいほせんせい)」とあだ名がつけられるほどになります。(推歩とは星の動きを測ること、つまり暦学のことです。)
¶ 地球の大きさを知りたい

当時、新しい暦の寛政暦(かんせいれき)を完成させた至時は「地球の大きさ」を知りたがっていました。暦局でも子午線1度の長さは25里~32里の間で意見が分かれていました。そこで忠敬は、深川の黒江町にあった自宅から浅草の暦局までの緯度の差がちょうど1分(いちぶ、1緯度の60分の1)だったことから、その距離を測り、方角と掛け合わせ、1631m(1度
にすると24.9里)と推定します。忠敬は、この結果を直ぐに至時に報告しますが、「距離が短すぎてこれでは誤差が大きいだろう。蝦夷(現在の北海道)から江戸までくらいの距離がないと、精度が得られないのでは」とアドバイスされます。実際、1分は1849.2m(1度にすると28.25里)ですので、かなりの誤差が発生していました。そこで、至時と忠敬は、なんとか蝦夷まで行くことは出来ないかと考えあぐねます。その頃の蝦夷は、ロシアから開国を迫られるなど、急を要していました。このような事情を利用して、至時は、地図を作ることを理由に蝦夷まで行くことが許可されるのではと思いつきます。そして、その目論見通りとなりました。
¶ 第1次測量…蝦夷
寛政12年閏4月19日(1800年)に忠敬は、富岡八幡宮に参拝した後、浅草の暦局から蝦夷へ出発します。この第1次測量が、後日振り返ってみると、長い長い測量の旅の始まりでした。奥州街道から蝦夷に渡り、松前を起点に根室半島まで1日40Kmを黙々と測量しながら歩いていきます。この時の測量は歩測でした。そして、同年10月21日に帰ってきます。出発してから、180日が経過していました。出来上がった地図を見た至時と幕府の要人は、今迄の地図とは全く異なるレベルの精度に大変感心したということです。そして、この事が、2次測量以降につながっていきます。
¶ 第2次測量以降…忠敬の測定方法

第2次測量では、相模・伊豆と本州東海岸を測定します。第1次測量では、スケジュールの関係から歩測しかできませんでしたが、今回は、しっかり日程を取り、測定していくことにしました。忠敬の測量というと、よく「両程車(りょうていしゃ)」と呼ばれる引いて歯車を回し、距離を測定する器具を思い浮かべます。しかし、街道でさえ、江戸時代は十分に舗装されていませんし、海岸線となるとデコボコが多く全く役に立ちませんでした。それではどうしたかというと、単純に距離と方角を計測していくという方法が取られました。まず、地形の曲がり角に梵天と呼ばれた目印を立てます。そして、その間の距離と角度を測り、地図を作成していく方法でした。距離は、間縄又は鉄鎖と呼ばれるもので測りました。また、角度は杖先羅針と呼ばれる杖の先に方位磁石を付けた物で測りました。これは、磁針を南北に合わせ、磁石の上に付いている覗尺(のぞきじゃく)を目標に向けて測定できるようになっていました。(忠敬の銅像にはこれを持ったものが多く見受けられます。)この長さと角度で測定していく方法は、導線法と呼ばれ、田畑や町を測量する際に用いられた当時最も一般的な方法でした。しかし、導線法は、繰り返していくと、誤差が積み重なっていきます。これは、公会法と呼ばれる方法で修正されていました。公会法では、まず寺社の屋根など周りより高くどこからでも見える目標物を設定します。そして、それを地形測定の基準点として方角を測り、修正していきます。(基準点で最も有名なものは、富士山です。)また、海岸線などでは、まず岸沿いに測った後、最初と最後の測定点を船を使って測り、誤差を修正する横切法が用いられていました。さらに忠敬は、昼は太陽、夜は星々の天体観測を行なっていました。この天体観測で得られた経緯度の測定結果で、大きな観点でも地図を修正していきます。このように地道な測定の繰り返しの結果、第2回測量後では、1分が1845.63m(1度にすると28.2里)という結果を得ます。これは、現在の数値と比較しても驚くべき精度でした。
¶ 第10次迄…17年間続いた測量の旅

忠敬は、第3次では出羽・越後、第4次は尾張・越前を周ります。この第4次の測量の旅は、享和3年10月7日(1803年)に帰ってきます。この時、地球の外周が約4万キロと結果が出るのですが、これは師の至時が入手したオランダの最新天文学書「ラランデ暦書」と数値が一致しました。師弟は手を取り合って大喜びしたといわれています。ただ、翌年の享和4年1月5日、忠敬にとって大変ショッキングな出来事が起きます。それは、忠敬の測量の旅を陰になり日向になり支えてきた至時の別れです。至時、39歳、道半ばの死でした。その年、忠敬は「日本東半部沿海地図」をまとめ上げます。そして、その地図は、当時の将軍家斉が上覧します。将軍を始め、立ち会った幕閣たちはその緻密さに驚愕したと言われています。その後、忠敬は御家人として召し抱えられ、以降、第5次からの測量の旅は、幕府から直轄事業となります。
その後、第5次は畿内・中国、6次は四国・中国、7次と8次は九州と段々と南下しながら旅を続けます。そして9次は、伊豆諸島、10次の江戸府内の測量が終わった頃は、文化13年(1816年)となっていました。実に足掛け17年もの間、測量と地図製作を繰り返したことになります。当初の編成は5人程度だったのですが、第5次以降は、幕府の直轄事業となったため、携わった人数も膨れ上がります。20人近くの編成となり、各藩からの協力者も合わせると100名もの人数に登ったこともあったようです。
¶ 隠された死
文化14年(1817年)、忠敬が72歳になった時のことです。かつて測量技術を教えた間宮林蔵が、蝦夷地(北海道)の測量データを持って訪ねてきました。これで、日本全国の地図が揃いました。ところが、この頃から忠敬は体調を崩します。長年の無理が祟って、歯もほとんど残っていない有様でした。そして、文政元年4月13日(1818年)、73歳で亡くなります。ただ、至時の息子、高橋景保たちは、なんとしても忠敬が作った地図として幕府に全日本全図を報告したいという思いがありました。そこで、そのまま忠敬の死をひた隠しにします。そして、高橋景保の監督の下、弟子たちなどによって完成され、文政4年7月10日(1821年)、「大日本沿海輿地全図」として、江戸城の大広間でお披露目されることとなります。忠敬の喪が発せられたのは、その翌々月の9月4日のことと言われています。忠敬は生前、「私が大事を成し遂げられたのは、高橋至時先生のお陰である。だから、どうか先生のそばに葬ってもらいたい」と、遺言を残していました。その願い通り、源空寺の高橋至時・景保父子の墓と並んで今も忠敬は眠っています。

¶ 国家機密だった伊能図

こうして作られた伊能図ですが、あまりに精密なため、国家機密として幕府の紅葉山文庫に大切に保管されていました。この書庫から解放され、庶民の手に渡るのは、この「大日本沿海輿地全図」が完成してから50年もの歳月が経過した明治になってからのことです。しかし、この精密な地図も時代の流れで、三角測量で計測した帝国図と少しづつ入れ替わっていきます。ただ、伊豆諸島南部にある青ヶ島を最後に完全に入れ替わるのは、昭和10年(1935年)のことで、この偉大な地図は、明治以降50年もの長きに渡り使われました。